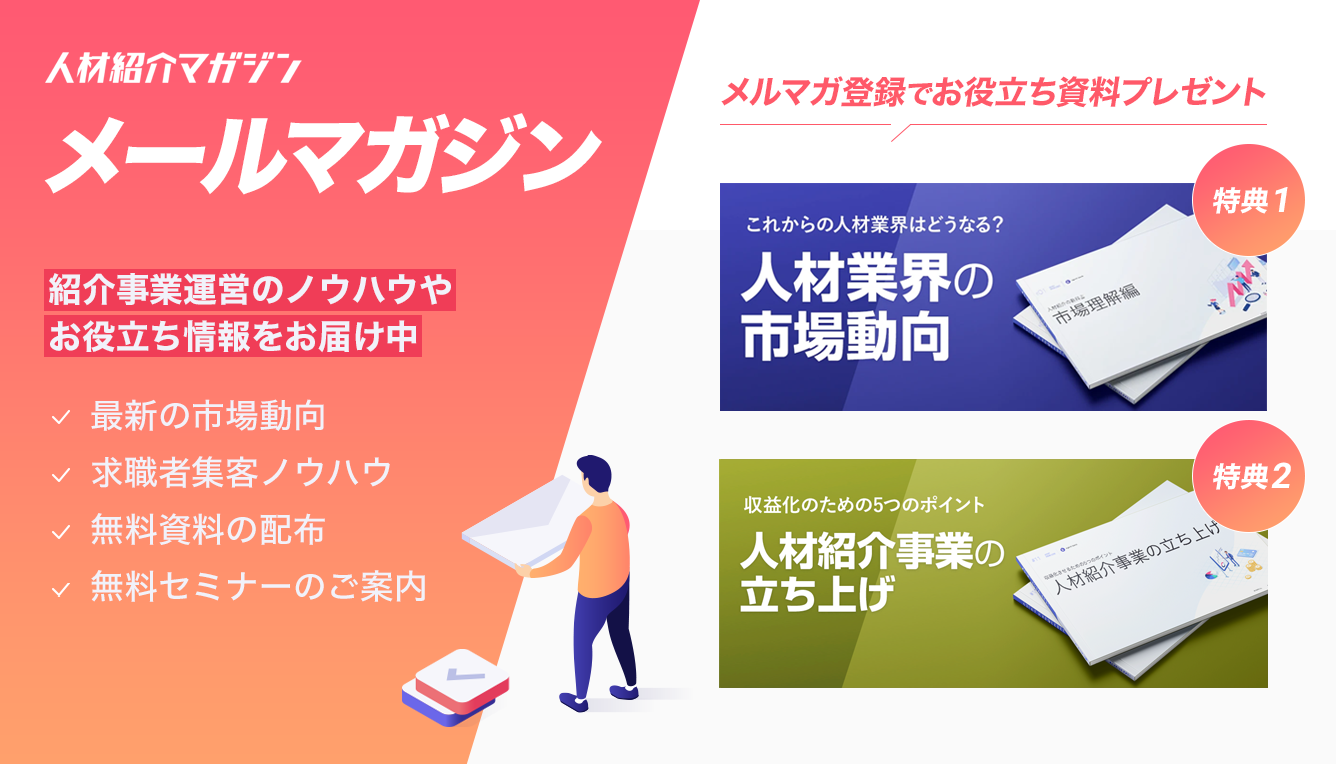プロフィール H&innovation株式会社 鈴木 利弘
プロフィール H&innovation株式会社 鈴木 利弘
早稲田大学を卒業後、読売新聞社に入社。巨人戦や箱根駅伝、美術展、落語など多くのイベントをプロデュースした後、35歳の時にキャリアチェンジしてリクルートに転職する。プレイングマネージャーとして広告営業を担当した後に、ベンチャー企業の営業部長や中国での新規事業立ち上げ責任者などを務めた。H&innovation株式会社に参画し、人材紹介事業部のトップとして事業運営に従事する。

Q.現在は求職者からの信頼も厚く、順風満帆に見えますが、当初からうまくいかれていたのでしょうか?
正直なところ最初の2年間は納得のいく事業運営ができていませんでした。人材業界は全くの未経験だったので、話を聞きに行ったり本を読んだりして、見よう見まねで事業運営をする毎日でした。
業界的に求人ありきで求職者をマッチングをするスタイルで事業運営している会社が多かったので、同様のやり方を真似することから始めていたのですが、自分自身が全く楽しくなかったのが、正直なところです。なにか違和感のようなものを感じながら事業運営していたので、いつ撤退しようかと考えていたこともありました。
Q.そこから現在のようなスタイルに変化されたのは、何か変化のきっかけがあったのでしょうか?
自分のキャリア面談に満足してくれた求職者が、知り合いを紹介してくれたことがきっかけでした。集客数を増やすというビジネス的な観点も大切ですが、それよりも自分の提供価値に満足してくれていることが実感できたのが嬉しかったです。
また、転職決定した求職者にヒアリングをしても、伴走型でキャリアコンサルティングをしたことに価値を感じてくれている方が多かったので、とことん自分のスタイルを追求しようと決意しました。
つまり、求人ありきで求職者を集客するのではなく、悩みを持つ求職者を集客し、その求職者ととことん向き合い、そのソリューションとして求人を紹介していくスタイルに大きく変えました。
Q.具体的に業務で変えられたことは何ですか?
求職者集客のためのスカウトメールの打ち方、1人1人の面談にかける時間、月間の面談人数、そして面談スタイルの全てを一新しました。
とにかく求職者にとって価値のあることが何かということを突き詰めて考えながら実行するということを繰り返しました。例えば、求人ありきにはしたくないので、スカウトメールに求人は一切添付しません。また、求職者1人には選考対策も合わせると10時間〜20時間くらいの時間をかけます。長い人は半年以上かけて転職活動を進めていきます。1人1人に多くの時間をかけているので、月の面談人数は多くても15名程度です。
2016年の秋からは、求職者ありきの視点で、すべての業務フローやKPIを変更しました。

Q.具体的にスカウトメールはどのような文面を送られているのですか?
以前の私と同様、多くのエージェントは求人の魅力で訴求して集客していると聞きます。しかしその時点で求職者が期待しているのは、エージェントに対する価値ではなく、求人に対する価値です。つまり、この時点でエージェントとして差別化するポイントを狭めてしまっていると思います。
私の場合は求職者が抱えていそうなキャリアにおける課題や悩みに徹底的にフォーカスし、その課題を約10種類に分類しています。求職者のレジュメを読み、仮説を立て、それに合ったスカウト文面を送り分けるようにしています。受けたい求人が決まっているのであれば転職サイトを使うはずなので、エージェントに期待しているのは、悩み相談でありその課題解決だと思っています。
Q.面談ではどのようなお話をされるんですか?
最初の面談ではその人の求める働き方とアピールポイントについて徹底的に深掘りしていきます。
何が好きなのか、得意なことは何かという部分を深掘りしつつ、未来の話を中心に雑談や質問を交えながら、一緒に整理していきます。 特に、自分の好きなことを好きに選べた学生時代の話などを深掘りすることは、その人が大切にしたいあり方や働き方という部分を明確にできるので重点的にヒアリングします。
こういった根底にある価値観や得意なことを明確にして、転職活動の軸として設定することにより、入社決定した後に転職先で活躍できる可能性も高くなると思っています。未経験のポジションであっても、その人自身が実現したい働き方を具現化できる仕事を選択できれば、2-3年くらいの経験差がある人を簡単に追い抜かすことができると考えるからです。
Q.求人紹介はどのようにされていますか?
お互いが納得いくまで話した上で、転職活動の軸が言語化ができれば、軸にあった求人を職種にこだわらず幅広くご紹介します。
もちろん業界や職種毎にまとめてご紹介するようなことは一切しないので、紹介求人に統一感がないように見えることもあるかもしれません。しかし根底にある軸の部分は一切ブレていないですし、本当にその人にマッチすると思うものしかご紹介はしません。
ご紹介後は、求人選択の理由をヒアリングし、それを参考にしながら紹介求人の精度をどんどん向上させていきます。
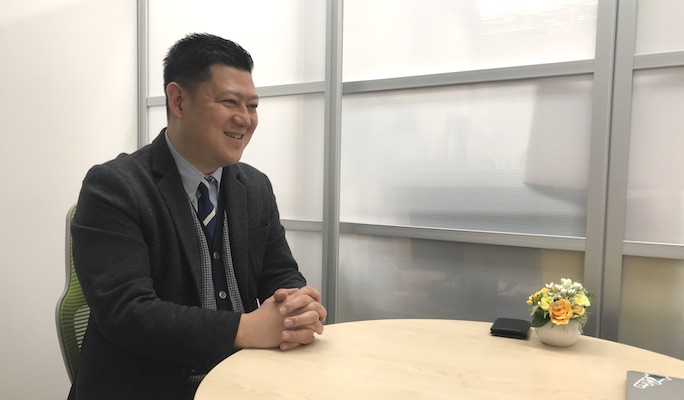
Q.選考対策で大切にされていることはありますか?
職務経歴書などの選考書類の添削にはとても力を入れています。
職務経歴書の書き方のような本に書かれているフォーマットでは、 その人自身の価値観や魅力が伝わらないことが多いので、既存のフォーマットにこだわらず、どうやったらその人らしさが伝わるのか徹底的に求職者と推敲していきます。 職務経歴書は A4で1.2枚でなければいけないというルールはありませんので、多い時は5.6枚になることもあります。
とにかくその人の魅力が伝わる形を追求していくので、人によってはエピソードだけで数枚の選考書類になることもあります。
Q.書類対策で多くの時間を割くのには、どのような理由があるのですか?
3つメリットがあると考えています。
1つ目は、応募要件に満たない部分がある場合にも、パーソナリティの部分をしっかり伝達することで、書類選考を通過する確率がぐっと上がります。
2つ目は、ある程度面接の内容をコントロールできることです。多くの面接官は、直前に経歴書の内容を見て質問をしてきます。つまり、選考書類を作り込むことで、求職者の魅力ポイントが伝わるエピソードに話題を集中させることができます。
3つ目は、自身の取り組みや強みを認識できるところです。求職者は選考書類を作る過程で、徹底的に考えアウトプットを繰り返すことになります。自分の考えが整理出来ますし、 何度も推敲したことにより内容に自信を持つことができ、面接でもしっかりと伝えることができるのです。
Q.面接辞退なども含めて、面接の進捗はどうでしょうか?
1次面接の通過率は5割を超えます。
これは徹底的に価値観に向き合い、受かる求人ではなく受けたい求人を受けてもらっているので、この数値は誇れるものだと思っています。また、面接辞退についてはむしろ推奨しています。面接でお互いのことを知った上で、転職活動の軸に合致しない場合には、お互いにとって良くないので、選考通過後であっても辞退すべきだとも伝えています。
また価値観をしっかり伝えられてる事例として、企業側から別ポジションを打診されるパターンもあります。面接官から、「より○○さんにぴったりの求人があるので、新しいポジションで選考を進めましょう」と言われることも多く、その人の価値観が適切に伝わっている事例だと捉えています。

Q.このように求職者に徹底的に寄り添うことで良かったことを教えてください。
入社後にも連絡を取り続けている求職者も多いので、活躍していたり楽しそうに働いている姿を見るととても嬉しいです。
事業的な観点から見ても、選考通過率の高さや内定承諾率の高さ、求職者の紹介の多さなどは、徹底的に求職者への提供価値を意識しているからこそ、高い水準を誇っている点は大きな利点です。こういうところが他社との差別化ポイントになっていると思います。面談を重ねているうちに、 「他のエージェントは断ってきちゃいました」と言われることも多いので、それも価値提供できている証拠だと思っています。
Q.「AIが仕事を奪う」という議論もありますが、エージェントはどうなると思いますか?
ただのマッチングではなく、求職者もしくは求人企業に寄り添い徹底的に価値提供できていれば、エージェントという職業はなくならないと思います。
私が求職者に提供しているものは、その人自身のポテンシャルを引き出すものであり、50%しかアウトプットできていない人に対して、それを100%に近づけるものだと思っています。そうすることで、なんとなく転職していくのではなく、自分に自信を持って転職していくので、入社後のパフォーマンスも高いです。
私はボクシングで言うトレーナーのようなもので、こういった人に寄り添って伴走するということは、 AI には絶対にできないと思っています。CA側に寄せて価値提供するのか、RA側に寄せて価値提供するのかを選択し、とにかく深掘りして行くことが大切だと思っています。
Q.最後に御社の今後について教えてください。
人材紹介という事業は、 確かに参入障壁が低いビジネスです。
しかしポジショニング戦略を考え、ある領域で圧倒的な独自の提供価値を磨くことができれば、他社には追随できないものになっていくと考えています。とにかく、求職者に寄り添い、その人のポテンシャルを最大限に引き出すというところにフォーカスし、今後も試行錯誤を繰り返して、求職者への提供価値を徹底的に追求していきたいと思っています。
このような成功しているエージェントは、AIに負けない人的な価値を大切にしています。
誰でもできる業務は、AIに置き換わってしまうかもしれませんが、それぞれの人と結びついた価値は一生消えることはありません。
今のうちから、自分のコア業務以外は外部サービスに任せて人的価値を磨いていきましょう。
※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。
編集部では、人材紹介に関する様々な情報を無料で提供しています。お気軽にご登録ください!