

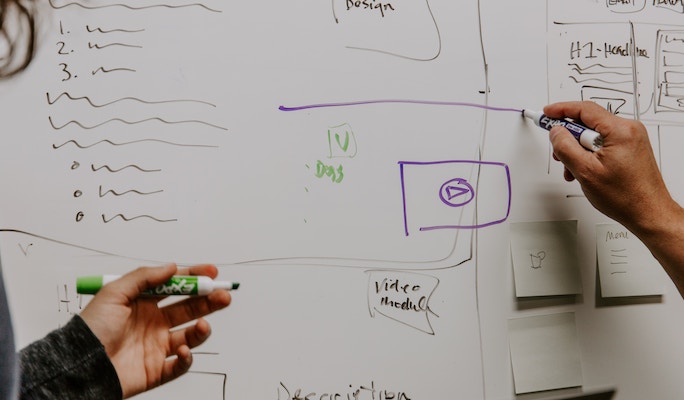
介護の仕事は「介護記録の記載」「おむつ交換」「入浴介助」「利用者とのコミュニケーション」など、担当者の拘束時間が長く、かつ精神的な負荷が大きい業務が多いことから不人気職種の1つ。
ただし少子高齢化が確実な日本では、介護人材の不足も並んで確実視されており、十分な人材の確保には「年間6万人」の採用が必要とも言われています。
現実的に「不人気職種」で、年間6万人の採用を実現するには、通常通りの採用だけでなく、ICT化による業務効率の向上や、採用プロセス/手法の見直し自体も必要でしょう。
介護人材の人手不足の原因と、採用課題の解決策を解説します。
そもそも介護職が、慢性的な人手不足に陥る原因には「要資格」の仕事であることが挙げられます。
介護職の資格は「介護職員初任者研修→介護福祉士実務者研修→介護福祉士→認定介護福祉士」の順で、より上位のものとなり、介護福祉士の資格を取るにはまず「受験資格」が必要。
福祉系の専門学校などに入学し、卒業すると介護福祉士の受験資格が得られます。

介護現場で3年間の実務経験を積み、国家試験を受けるルートもありますが「3年の実務経験」「専門学校」いずれも「国家資格の受験」そのもののハードルが高いことは否めません。
「有資格者でなければできない仕事」と「気軽なアルバイトなどでも可能な仕事」に、仕事そのものを切り分けていくことは最低限、今後は重要でしょう。
介護の仕事がきついとされる要因には、前述の通り「おむつ交換」「入浴介助」などが主に挙げられます。
一方で、目に見えづらいものの現場に大きな負荷を与えている業務には「介護記録の記載」も挙げられます。
介護記録とは「スタッフが利用者に行ったサービス」「利用者の状況やサービスへの反応」「その後の変化」などを主に記載するもの。所轄の自治体や利用者から記録の開示を求められることがあるため、介護施設では記録を行うことは必須です。
介護記録は「紙で管理している」施設も少なくなく、手書きで書く工数が大きいもの。また介護した人数分を1日の終わりにまとめて書く必要がないため「記録そのものにかかる工数」があります。
電子化等による効率化の余地が大きい業務と言えます。
厚生労働省の試算によると、少子高齢化の進行によって、2025年度には介護職員が約253万人必要とされます。
一方で2025年度時点での、介護人材の供給見込みは約215万人。 およそ38万人の介護職員が不足する試算となります。
2021年から2025年の5年間で、介護人材を十分に確保するには毎年6万人~7万人の介護人材の確保が必要です。
![]()
不足する介護人材の受け入れに当たっては、東南アジア等の「外国人人材」の活用も期待されています。しかし前述の通り、そもそも介護職は「介護福祉士」の資格取得ハードルが高い上、求められる日本語スキルも高いことから、受け入れ人数が伸び悩んでいることも現実です。
介護福祉士の資格がなくともできる業務の範囲を拡大したり、そもそも国内人材の活用法を一層検討するといったことも必要でしょう。
毎年6万人の介護職を確保するには、現実的には「業務効率化」を前提として推し進めたうえで、介護福祉士の資格を持たない人材を「サポート」として積極登用。加えて人材紹介会社の活用も検討すべきでしょう。
1つ1つ解決策を、解説します。
介護記録を「1日の終わりにまとめて付ける」のではなく、たとえば体温測定の度にクラウド経由で記録し、データベース化するといった工夫が考えられます。
従来の介護記録は、血圧や体温は「まず紙にメモしたうえで、清書、もしくはExcel等に記す」とい二度手間が主流。
一方で、ICT化すると測定と同時にシステムにデータを入力すれば記録が完了します。ICT活用や各種クラウドサービスの導入余地は大きいです。
介護の現場は、要介護者の高齢者のケアをしていることもあり「突発対応」が多くなりがちです。よって電話でのやり取りや、口頭の伝達が増えやすいです。しかし、こうしたコミュニケーション手法は「認識の齟齬」や「言った/言わない」の論争を生みやすいものです。
そこでSlackやチャットワークといったビジネスチャットを導入し、原則として「マスト対応の指示はすべてチャット化」することで、言った/言わないを未然に防止可能。
電話や口頭伝達の回数を軽減することで、コミュニケーションコストを軽減しつつ、後から業務内容を簡単に振り替えることもできます。
毎年6万人の新規採用を行うと、業界全体に「未経験者」や「外国人」も増えていきます。経験豊富な介護福祉士であれば「言わなくても分かる」ことでも、新人には全く伝わらないということは珍しくありません。
そのため「マニュアルを充実させる」ことは絶対条件として必要です。将来的なスタッフの教育コストが軽減されます。
介護福祉士が担当している業務には「介護福祉士でなくてはできない仕事」もあれば、「介護福祉士でなくともできる雑務」もあるでしょう。
要介護者の体に直接触れる業務は「介護福祉士」でないと難しいですが、清掃や事務作業のサポート、介護記録のサポートといった「アシスタント」的な役割であれば、研修中の人材や無資格者でも可能でしょう。
有資格者を本来的な介護業務に集中させられるような、環境づくりも重要です。
人材紹介会社の活用も視野に入ります。外国人人材や無資格者を現場で有効活用し、ICT化にも対応した経験がある国家資格保有人材であれば「介護職のヘッドハンティング」も検討しても良いでしょう。
短期的には「担当している高齢者の面倒を見れなくなる」点で心苦しいかもしれませんが、好条件の現場に移るということが一般化すると、中長期で見て現場の待遇改善が一気に進みます。
最後に介護職の「人材紹介」の可能性を解説します。
まず短期的に見ると、未経験者や外国人人材の活用は避けては通れません。一方で「国家資格が必要」で、そもそも国家資格の受験そのものにも要件が定められている現状があります。
外国人人材や未経験者を募集し、一定期間の研修を実施。
研修を通じて「実務経験さえ積めば、間違いなく介護福祉士の資格が取得可能」な人材を見極めて「高品質な無資格者」だけを紹介するといった手法には、一考の価値があります。
こうした「研修済みの未経験者」を紹介するビジネスモデルは、既にITエンジニア職など他業種では大きな広がりを見せています。
特に「認定介護福祉士」は、介護の現場で豊富な経験を積み、多くの未経験者や外国人人材のマネジメント経験もあると考えられる国家資格保有者です。
介護の現場の理論年収は低いのが現状ですが、保有しているスキルセットを見れば高年収を得てもおかしくない人材でしょう。
たとえば外国人人材のマネジメント経験を持つ「認定介護福祉士」をスカウト。今後、外国人人材や未経験者の受け入れを加速させようとしている大型の介護施設とマッチングさせ、本人の待遇も大きく引き上げるということも一考の余地があります。
介護が「不人気」「人手不足」になりやすい理由と、採用課題の解決策を解説しました。
現実的に介護職は、需要の急拡大に対し、国家資格が悪い意味で「ハードルが高すぎる」のが現状。外国人人材の受け入れも、未経験者の積極登用も「期待されるほどには伸びていない」のもまた現状です。
さらなる法改正も期待される現状ですが、一方でテック活用や、また優秀な人材のヘッドハンティングなどまだまだ改善の余地もあります。
人材紹介マガジンを運営する「agent bank」は、中小の人材紹介会社の売上改善の相談や各種ソリューションの提供、また人材紹介業の免許取得サポートを行っています。人材紹介業への参入を検討中の方や、売上改善を行いたい方はお気軽にご連絡ください。
※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。