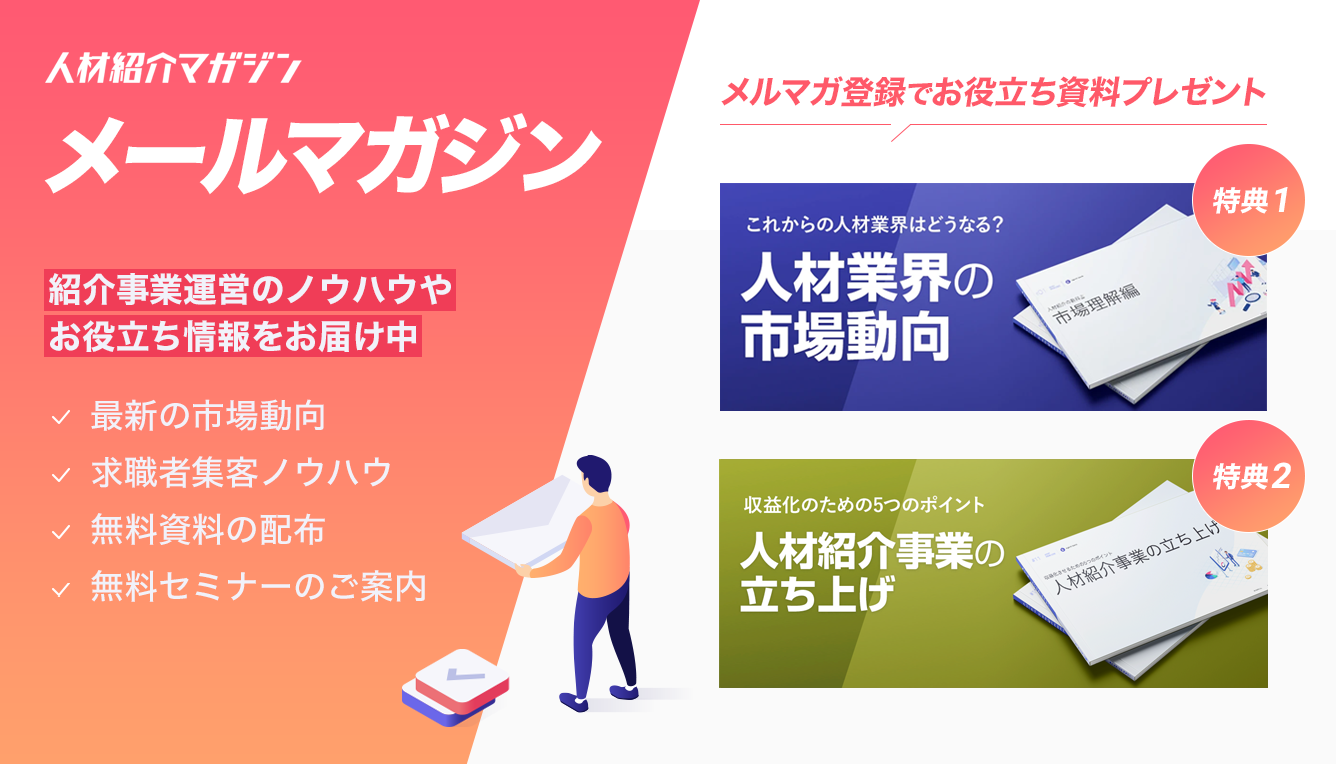今回は人材業界の市場規模を、主要3業界(人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業)のデータをもとに考察していきます。
また記事の後半ではコロナ以後の動向も見ていきます。

まずは人材ビジネス3業界(人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業)の市場規模を、2021年度の統計を踏まえて解説いたします。
株式会社矢野経済研究所の調査データをもとに、1つ1つ見ていきましょう
(※1)
![]()
2021年度の人材派遣業の市場規模は、9兆2,000億円(前年度比6.6%増)。ちなみにコロナ前、2019年度の市場規模は7兆8689億円。新型コロナの感染拡大は、非正規雇用である派遣業の市場拡大にはプラスに働いたと言えるでしょう。
一般社団法人日本人材派遣協会によると、総務省が2021年度に集計した派遣労働者の総数は142万人(※2)。
職種別派遣社員数で見ると、男女計では「事務職」が48万人(34.3%)ともっとも多く、「製造関連職」が35万人(27.0%)、「運搬・清掃・包装関連職」が22万人(15.7%)と続きます。特に事務職の派遣は、就労人口の減少などを背景に採用ニーズが伸長。2019年度には43万人だった派遣社員数が、2021年度には5万人増えています。
またITエンジニアや介護系人材は慢性的な人手不足の業種であり、派遣業界においても人材供給が不足している状態となっています。
![]()
2021年度の人材紹介業の市場規模は、2,960億円(同17.5%増)。
なおコロナ前、2019年度の市場規模は3,080億円。2021年度にかけて徐々にアフターコロナに移行し、「コロナ前に近しい規模」へと回復したと言えます。
人材紹介業は、人材派遣業と比較すると人材業界での売上高は小さいのが現状です。しかし2009年度以降、右肩上がりでの市場拡大が続く成長産業であることも事実です。
同じく矢野経済研究所の調査によると、2010年度の人材紹介業の市場規模は前年度比111.8%の850 億円。
2010年度と2019年度の市場規模を比較すると、9年間で3倍以上の市場拡大が起きていることが分かります。

2021年度の再就職支援業市場の市場規模は、321億円(同5.2%増)。コロナ前、2019年度の市場規模は248億円でした。コロナ禍に飲食業や観光業で休職者や退職者が急増したことから、再就職支援の需要が急進。この3年間で市場規模が拡大しています。
ちなみに人材ビジネス3業界のうち、人材派遣業と人材紹介業は好況時に市場が拡大する傾向。一方で好況時は再就職が容易になることから、再就職支援業は成長が鈍化する傾向にあります。

続いて、人材業界の業界地図を見ていきましょう。大手各社の売上高や年収を紹介します。

人材業界3ビジネスのうち、近年続いているのが「人材派遣業者の人材紹介業への参入」です。
派遣業は最低賃金の引き上げや、労働者派遣法改正(2015年9月施行)による「3年ルール」の導入など法改正が続き、利益率が低下。
2020年現在、派遣業が人材業界3ビジネスの中でもっとも市場規模が大きい業種であることに変わりはありません。しかし、各社がより利益率が高い新業態を探る中で、人材紹介業に対する関心度が高まっていると言えるでしょう。
派遣会社による人材紹介会社設立の背景などは、こちらの記事で解説しています。

ここまで、人材業界の市場規模や業界地図を1つ1つ解説してきました。派遣業や再就職支援の市場規模が伸長していることから分かるように、非正規雇用や再就職のニーズが拡大。一方で「正社員の人材紹介」はコロナ禍で逆風に晒されたものの、アフターコロナに移行し、市場に活気が戻りつつあります。
新型コロナウイルス以後の人材業界の動向を1つ1つ、見ていきましょう。

コロナ以後の人材業界の動向は、まず「短期的な展望」と「中長期的な展望」を分けて考える必要があります。
短期的には「コロナ前の水準の有効求人倍率への回復」こそ達成されたものの、非正規雇用での採用への需要が極めて大きいことは事実。各社でテレワークを前提に、業務委託人材の活用も進む中で「正社員採用数」が今後どこまで伸びていくかは要注目のポイント。
中長期的には、少子高齢化による労働力人口の縮小が人材業界の大きな課題となるでしょう。中高年の就業希望者の円滑な転職を実現する仕組みづくりが求められるでしょう。
まずは新型コロナ感染拡大の影響を改めて振り返りましょう。日本では2020年4月7日に、政府が緊急事態宣言を発令。2020年3月ごろから人材ビジネス各事業者の業績に悪影響が出始めました。コロナ禍での正社員有効求人倍率の推移は、下記の通りでした。
有効求人倍率は1を上回れば売り手市場、下回れば買い手市場です。各国で渡航制限が続き、観光需要が低下。
2020年第2四半期の貿易量も新型コロナの影響で前期比14.3%減と急落(※3)するなど、国内だけでなく、世界的に見ても経済情勢の不確実性が高い状況が続きました。
一方で2022年に入ると有効求人倍率が大きく改善に転じ、2023年現在はコロナ前の水準まで回復しています。とはいえ「正社員採用」の需要がどこまで回復、伸長するかは大きな論点。2020年以降、人材紹介業が伸び悩む半面で、非正規雇用である人材派遣業は大きく拡大。非正規雇用への需要の大きさが良くも悪くも浮き彫りになったのも事実です。
総じて、正社員採用ニーズの回復はある程度見えたものの「どこまで伸びるか」は注目点です。
コロナ禍の有効求人倍率や採用市場の動向は、こちらの記事でも解説しています。
![]()
中長期的には、少子高齢化による労働力人口の減少は避けられません。
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」によると、高齢化率は2024年に30.1%となると予測されています。50歳以上の人口が5割を超えるとも言われており、2024年以後の人口ピラミッドをめぐる課題は「2024年問題」と呼ばれています。(※4)
一般的に採用サイドは、企業文化への適応性や教育による「伸び代」を高く評価し、若年層の転職志望者を好む傾向にあります。
しかし、現実的には若年労働力の減少は避けられず、中高年層の熟練技能や経験値を適切に評価し、企業と個人をマッチングする試みが人材業界には求められるでしょう。
また国内だけではまかないきれない若年層の労働力を、AI(人工知能)やRPAによる業務自動化、あるいは外国人労働者の確保によって補う工夫も求められると考えられます。
企業の副業解禁やジョブ型雇用の推進などの影響から、労働市場では転職者数の増加や、個人の転職回数の増加が予測されます。
また経済の不確実性が高まる中で、企業側が雇用の柔軟性を求める傾向が強まっていることも転職需要の拡大に寄与。
加えて個人の仕事観が変わり、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっていることから、「企業の採用ニーズ」「個人の就業ニーズ」のマッチングの難易度もやや上昇しています。
業種、職種を跨いだより多くの労働移動や、就業意欲の高い中高年の転職需要への対応など、企業と個人双方の多様なニーズをすり合わせた上でマッチングさせる高度な雇用の需給調整機能は今後も強く求められるでしょう。

長らく売り手市場が続いたIT関連の人材ビジネスにも、新型コロナウイルスの影響は及んでいます。
矢野経済研究所の調査では、2019年度のデジタル人材関連サービス市場規模(デジタル人材育成・研修サービス、デジタル人材派遣サービス、デジタル人材紹介サービス3市場の合計)は前年度比13.5%増。市場規模は9090億円。
しかし、2020年度はデジタル人材育成・研修サービス市場とデジタル人材派遣サービス市場は前年度割れが見込まれています。
デジタル人材の市場のボリュームゾーンは「人材派遣」です。派遣領域の前年度割れの原因は、外出自粛などによる派遣技術者の配属の遅れと景気悪化に伴う派遣活用の縮小。デジタル人材の中でも、高度な専門知識がそれほど求められない領域で派遣の活用が減少しました。
一方で、高度な技術を持つデジタル人材へのニーズは継続しており、デジタル人材紹介の領域は引き続き拡大見込みとされています。
全体の市場規模も2020年度は前年度比1.4%減の8,965億円を見込むも、2021年度は拡大傾向。2021年度の市場規模(見込み)は、9135億円と予測されています。(※5)
人材業界の市場規模、業界地図やコロナ以後の動向を解説しました。
2019年度時点では、人材業界の市場規模は7兆128億円でした。そして2021年度には9兆5,281億円まで拡大。そのうち9兆2000億円を人材派遣業が占めており、コロナ禍での非正規雇用の採用ニーズは強く、アフターコロナの2023年現在でも「非正規雇用」の市場は活性化しているものと見られます。
一方で人材紹介業もコロナ前水準まで採用ニーズが回復しています。高度な雇用の需給調整機能へのニーズは高く、中期的に見て今後の日本では転職者数も個人の転職回数も増加していくと見られます。
ぜひ、今回紹介したデータを転職市場の分析やコロナ以後の動向の予測に役立ててください。
(※1)労基旬報「人材ビジネス市場規模9.5兆円、うち人材派遣業が97%」
(※2)一般社団法人日本人材派遣協会「派遣の現状」
(※3)JETRO「第2四半期の世界貿易は新型コロナで急減」
(※4)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」
(※5)デジタル人材関連サービス市場に関する調査を実施(2021年)
※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。
編集部では、人材紹介に関する様々な情報を無料で提供しています。お気軽にご登録ください!