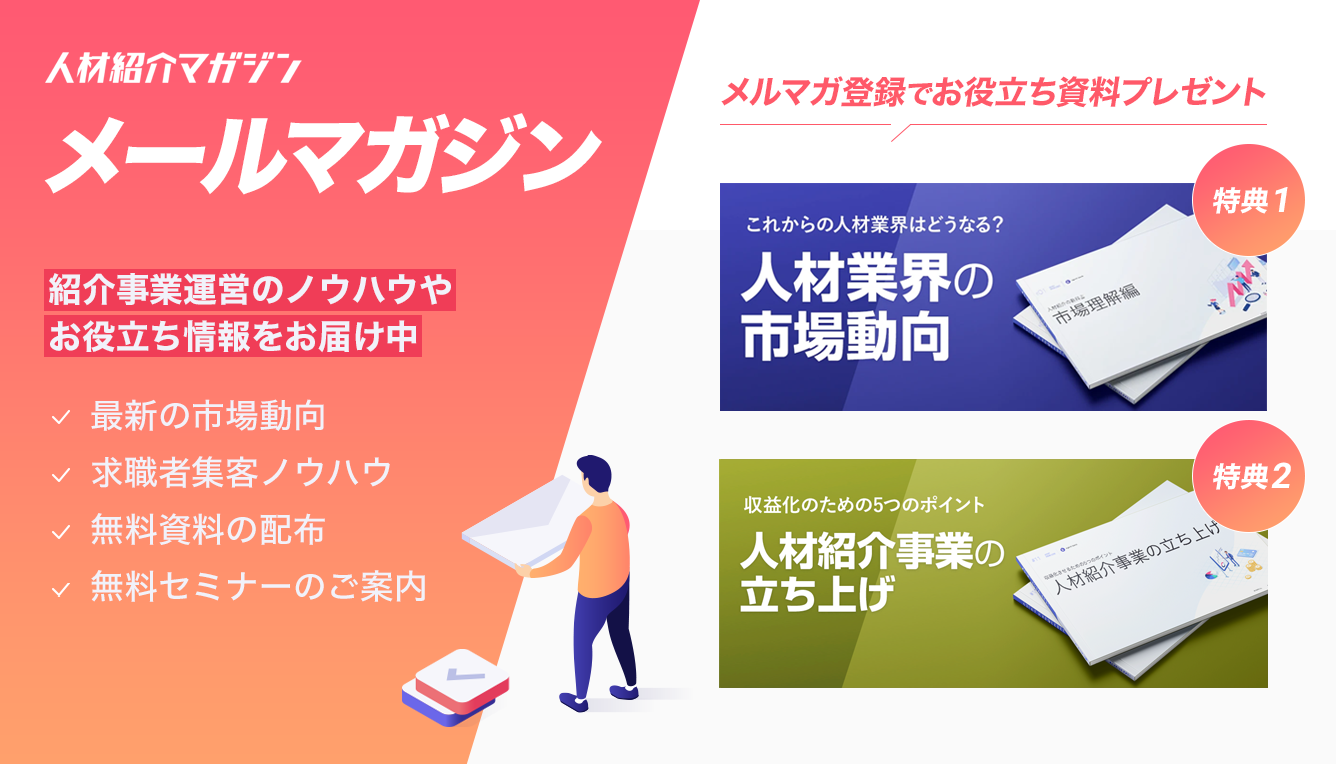人事や採用業務にAI(人工知能)やクラウドなどのテクノロジーを応用し、人事業務を効率化。事業者の生産性を高める「HRテック」が注目を集めています。
HRテックの一環として、人材紹介業においても事業者向けのクラウドサービスが広まり始めています。
今回は、人材紹介会社向けのクラウドサービスを総称して「人材紹介プラットフォーム」と呼称。人材紹介プラットフォームの例を紹介します。
また人材紹介会社向けのサービスを運営する際には、プラットフォームの運営元にも有料職業紹介の許認可取得が求められるケースがあります。HRテック事業者にも免許取得が必要な理由や免許を取得しない場合のリスクも考察していきます。
「人材紹介プラットフォーム」とは、HRテックの広まりの中で人材紹介会社向けのITサービスを総称するものとして使われ始めた言葉です。
明確な定義が存在する言葉ではなく、メディアによっても少しずつ単語が指す意味合いは異なっています。
今回の記事では、人材紹介プラットフォームという語句を「人材紹介会社向けのクラウドサービス」の総称と位置づけ。
代表的なサービスとして「求人データベース」などを紹介します。
人材紹介プラットフォームの例には、以下のようなサービスが挙げられます。
・求人データベース
・求職者集客向けサービス
・求人情報専門検索サービス
求人データベースとは、クラウド上で公開されている求人案件に求職者をマッチングさせることで人材紹介業を運営できるサービス。
人材紹介会社にとってのサービスの利用メリットは求人案件獲得のための法人営業コストを押し下げることが可能な点。
代表的なサービスには、人材紹介マガジンを運営する「agent bank」が展開する「agent bank」があります。
求職者集客向けサービスとは、人材紹介会社向けに求職者の獲得をサポートするもの。
異業種の方が「人材紹介」に関するサービスを立ち上げようとするとき、ネックとなるのが「サービスの立ち上げに人材紹介業の免許が必要となるケースがある」ことを認識していない場合があることです。
人材紹介プラットフォームの運営にも「有料職業紹介(人材紹介)」の免許が必要なケースが存在します。
具体的には「そのサービスが求職者と求人者のマッチングの成立をあっせんしているかどうか」が許認可取得の必要性の判断基準になります。
何をもって「マッチングの成立をあっせんしていると見なすか」はケースバイケースであり、社内の法務部や必要に応じて厚生労働省の雇用調整事業課に問い合わせて判断を仰ぐべきでしょう。
とはいえ、人材紹介プラットフォームに位置づけられる利益率の高いサービスのほとんどは「あっせん」の要素を持っているとみなすこともでき、免許を取得する方が法的リスクの面では安全です。
人材紹介マガジンを運営する「Zキャリア プラットフォーム(旧agent bank)」を例に解説します。
Zキャリア プラットフォーム(旧agent bank)は、求職者集客と求人開拓の両方をサポートする「人材紹介プラットフォーム」です。
たとえばZキャリア プラットフォーム(旧agent bank)が提供するサービスの1つに「求人データベース」があります。
Zキャリア プラットフォーム(旧agent bank)に公開されている求人案件に自社でサポートしている求職者をマッチングすることで人材紹介業を運営可能です。
Zキャリア プラットフォーム(旧agent bank)を運営する株式会社ROXXは、有料職業紹介事業の許認可を取得しています。
株式会社ROXXの事業所の名称、所在地、許可番号は以下の通りです。
株式会社ROXX
有料職業紹介事業 (13–ユ–307543)
本社:東京都新宿区新宿6丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア8階
繰り返しになりますが、プラットフォーム運営者にも人材紹介業の免許が必要か否かは「あっせん」の有無によります。
あっせんの定義についてはこちらの記事で解説しています。
たとえばプラットフォームの運営者が、求人者(企業)の希望に応じて求職者をフィルタリングできるような機能を提供していたり、双方の連絡を仲介したりトラブル発生時に介入することは「あっせん」に該当する可能性があります。
あくまで人材紹介業の許認可を取得せず、なおかつプラットフォームを運営するには「あっせん」の要素を持たないサービスにする必要があります。職業紹介ではなく、求人情報等の「情報提供」の範疇にサービスをとどめることが重要です。
自社が計画しているサービスが「客観的に見てもあっせんの要素を持たないか」や「法的なリスクはないか」はシビアに判断する必要がある事項です。
少しでも不安要素があれば、法務部や社労士、厚生労働省の担当窓口と連絡を取り合い免許取得の必要性を慎重に判断すべきです。
プラットフォーム運営者が免許取得をしないことで発生するリスクとして、最も大きなものは「何らかの理由で免許取得が必要となった場合に3か月以上の時間を要し、その期間はサービスを停止せざるを得ない可能性がある」ことです。
人材紹介業の許認可取得には、準備を開始してからおよそ3か月程度の期間を要することが多いです。
たとえばサービスのローンチ後に労働局からの指導によって「有料職業紹介に該当する」と見なされた場合、免許を後から取得しなくてはいけません。
免許取得には長い時間を要します。一度目の申請で許認可が下りなかった場合、申請のやり直しから免許取得には再び3か月の時間が必要です。
ローンチ後に外部からの指摘で「サービスが長期間停止する」という事態が発生し得ることが、リスクです。
逆に言えば、HRテック事業者は有料職業紹介免許の取得によって大きく事業範囲を広げることができます。
免許取得をしない場合、サービスの範囲は「情報提供」に留める必要があります。なおかつ「どこからどこまでが情報提供に合致し、どこからがあっせんなのか」という慎重なリーガルチェックも求められます。
一方で人材紹介業の免許を取得していれば、あっせんの要素を持つサービスも提供可能。マッチング成立時の利益額と利益率も大きいです。
事業範囲の拡大を目指しているHRテック事業者は、積極的に免許取得を検討する価値があるでしょう。
人材紹介プラットフォームについて紹介しました。
人材紹介プラットフォームには多様なビジネスモデルがありますが、中でも「あっせん」の要素を持つサービスはプラットフォーム事業者も有料職業紹介の免許取得の必要があります。
人材紹介プラットフォームの運営を検討している方は、サービス開発そのものの工数だけでなく「免許取得にかかる工数」も慎重に見積もりしましょう。
※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。
編集部では、人材紹介に関する様々な情報を無料で提供しています。お気軽にご登録ください!