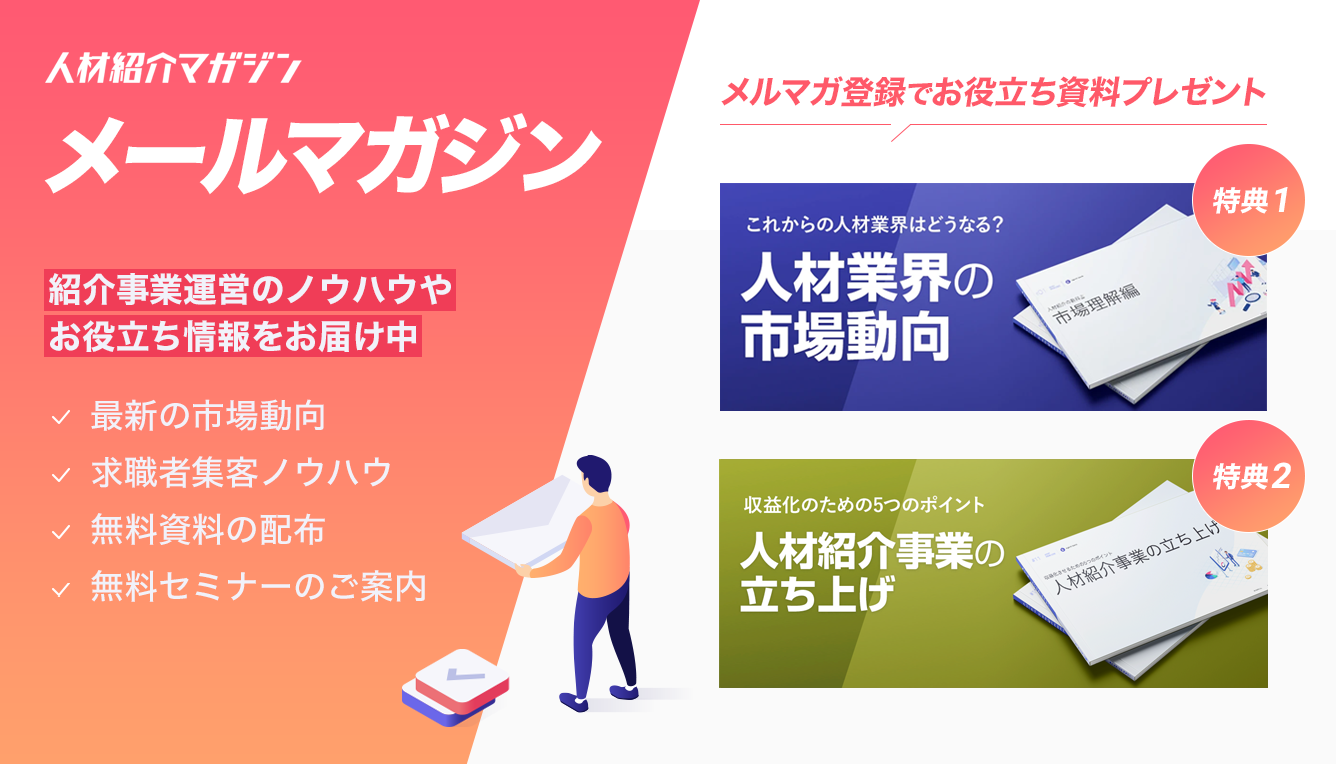今回は人材派遣業の立ち上げ方と、事業成功のために重要な6つのポイントを解説します。
人材派遣業は、許可要件を満たしていれば個人で事業を立ち上げることも可能です。ただし求められる要件は高く、なおかつ利益率が低いことも現実です。
立ち上げるだけでなく「成功する」ためのポイントを1つ1つ見ていきましょう。
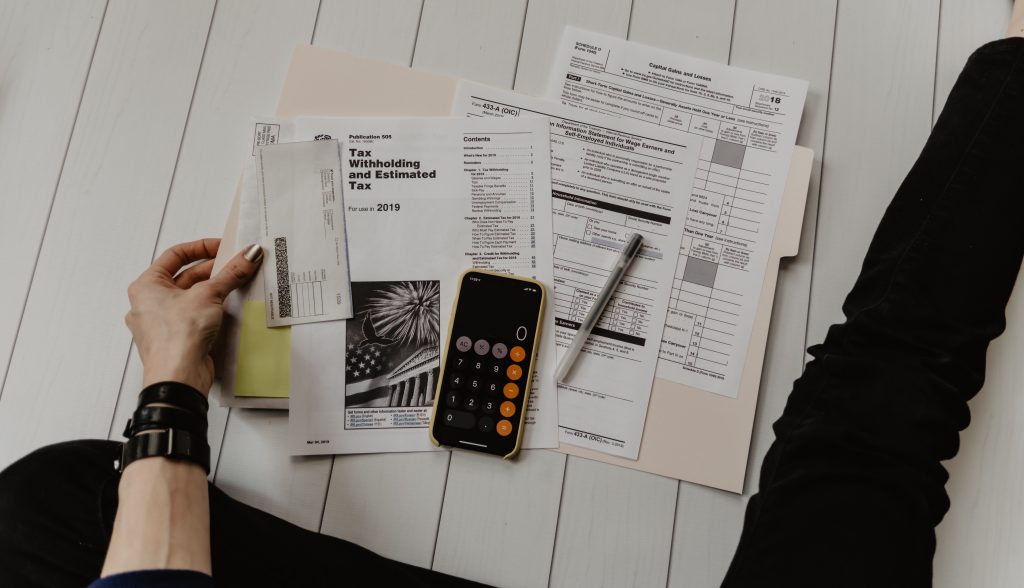
まずは人材派遣業の立ち上げ方について、解説します。

人材派遣業とは派遣会社(自社)が、雇用するスタッフを派遣先企業へと紹介する人材ビジネスのことです。
スタッフは派遣先企業の指揮命令下に置かれ、業務を行います。
労働者派遣法では「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」と定義されています。
人材派遣業のより詳細な定義や変遷、動向などはこちらの記事でまとめています。
人材派遣業は、個人でも立ち上げ可能です。
ただし個人事業主として開業する場合にも、法人とほぼ同等の手続きを行い、許可要件を満たすことが必要となります。
許可要件としては、以下の項目が定められています。
また資産要件の見方は、個人と法人で異なります。個人の場合は、確定申告書ベースで資産要件を満たす必要があります。
詳細な要件は、こちらの記事でも解説しています。
人材派遣業の立ち上げには、資産要件を満たすことやオフィス準備がまず必要。そして派遣元責任者講習の受講などの、許認可申請準備も求められます。
こちらの記事で、人材派遣の起業に必要なことを網羅的に解説しています。併せて参考にしてください。

ここからは人材派遣業の立ち上げを成功させるための6つのポイントを紹介します。
まず前提条件として、派遣業立ち上げの許可要件を満たすことが必要です。
という許可要件を満たすことは簡単ではありません。
特にベンチャー・スタートアップで派遣業を立ち上げる場合、資産要件をクリアするためには増資や個人名義での借り入れが必要となることもあるでしょう。
人材ビジネスへの参入を検討しているものの、許可要件を満たすことが難しい場合には、より要件が緩い「人材紹介業」の起業を検討するのも良いでしょう。
人材紹介業の開業に関しては、こちらの記事でまとめています。

派遣会社にとっては「派遣先企業」「派遣スタッフ」の双方が、顧客となります。双方をマッチングさせ、安定的な就労を実現することで、初めて自社の利益が生まれます。
よって派遣先企業と派遣スタッフのマッチングを意識しつつ、それぞれ別個に営業戦略を立て、効率的にアプローチする必要があります。

派遣先企業の獲得のためには、まず「企業側の採用ニーズ」を読み解く必要があります。
採用ニーズを読み解く際に、もっともシンプルな指標は業界ごとの有効求人倍率です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、正社員有効求人倍率は1.0を割り込むなど、全体的に低下傾向です。一方で業種別に有効求人倍率を見ていくと、高い数値を保っているものもあります。
例えば慢性的な人手不足が各社で続くITエンジニアの有効求人倍率は、2020年4月時点で2.38倍(※1)。
また医療や看護の業界でも、高い採用ニーズが安定的にあります。
このように採用ニーズが高い業種の企業に対して、労働力の確保の手段として「派遣」を提案するのは1つのアイデアでしょう。
こちらの記事では、コロナ禍の有効求人倍率について解説しています。

また、不況時の「固定費の削減ニーズ」に着目することも手です。
景気が悪化すると各社は人件費の削減を検討します。とはいえ人件費を削減したとしても「誰かが業務を担当する必要がある」ことも確かです。
正社員の給与のように「固定費」ではなく、売り上げに応じて増減する「変動費」として計上できることが派遣先企業にとっての「派遣社員を活用するメリット」です。
固定費の削減を検討している企業に対して、変動費で活用できる高品質人材として派遣スタッフを提案するのも良いでしょう。

派遣会社にとって、大きな課題の1つは「優秀な派遣スタッフ」を確保することです。
優秀な派遣スタッフを抱えている企業であれば、派遣先企業を探すこと自体はそれほど難易度が高いことではありません。
一方、有効求人倍率が低下する中で「未経験者」「ポテンシャル採用」の求人は減少傾向。実務経験が浅いスタッフを採用する企業は少ないのが現状です。この現状は正社員に限らず、派遣やフリーランスでも同様です。
派遣スタッフを獲得するには、求人広告やリファラル採用など地道な広告戦略が必要です。加えて「他の派遣会社と異なる、自社の強み」をアピールすることも重要です。
たとえば近年、派遣社員の待遇改善を目的とする「同一労働同一賃金」に注目が集まっています。
同一労働同一賃金については、こちらの記事で解説しています。
優秀な派遣スタッフにとっては、派遣社員という雇用形態のまま正社員同様の福利厚生が受けやすくなり、キャリアの選択肢が広がっている状態と言えます。
これから派遣として働く人にとっても「幅広いキャリアの選択肢」や「充実した福利厚生」は魅力的な要素に映るはずです。
たとえば「派遣スタッフに対する手厚い教育」「給与の高さ」「充実した正社員登用制度」など様々な福利厚生をアピールできると、派遣スタッフ獲得に向けては有利になるでしょう。
派遣スタッフは派遣会社に雇用される一方で、派遣先企業の指揮命令下に置かれているという特殊な状況下で業務を行います。
派遣先企業では、いわば「よそ者」。
「同一労働同一賃金」の考え方が広がりだしているとは言え、現場レベルではいまだに派遣社員は「正社員との間に壁を感じる」「今後のキャリアの展望が描けない」と悩んでしまうケースも少なくありません。
派遣会社には同一労働同一賃金の考え方に基づいた派遣スタッフの待遇改善に加え、こまめなキャリアカウンセリングや教育機会の提供が求められます。
派遣先企業と、派遣スタッフの間にはトラブルや苦情もつきものです。
派遣先企業が派遣社員に業務を発注する際の、大きな動機は「業務の効率化をはかりたい」「社内に人材がいない」といったものです。
つまり、派遣スタッフにとっては「業務量が多い」一方で「質問できる相手があまりいない」「その業務に精通している正社員が少ない」といったことが起こり得ます。
派遣スタッフの側から、勤務条件の見直しや契約の終了を求められることも時にはあるでしょう。
派遣会社は派遣スタッフと派遣先企業の間に立ち、双方の疑問やクレーム、トラブルに対応しながら良好な関係をキープする必要があります。
特に派遣先企業・派遣スタッフの数が増えていくほど、適切な労務管理や、一人一人の就労環境を細かくチェックし続けることは困難になっていきます。一方で労務管理を怠ると、トラブルが深刻化することもあります。
自社の規模感に応じた、適切な労務管理体制を常に探ることは非常に重要です。最低限、電話やメール、アンケートなどで常に派遣スタッフに対するフォローアップを行うことは大事です。

一般社団法人日本人材派遣業界のデータでは、人材派遣会社のマージン(手数料)のうち「営業利益」は、わずか1.2%です。
データの詳細はこちらにまとめています。
人材派遣業界は市場規模は大きい反面、極めて利益率が低い業界だと言えます。
「同一労働同一賃金」「最低賃金のアップ」など固定費が上昇傾向にある一方で、有効求人倍率は低下傾向。わずか1.2%の利益率は、今後さらに低下する可能性を秘めています。
人材派遣業界は、2020年〜2021年にかけて難しい状況下に置かれていると言えるでしょう。
収益性の上昇を目指し、派遣業界では事業の多角化が進んでいます。一例は派遣業による、人材紹介業の立ち上げです。
こちらの記事では、派遣業者による人材紹介業立ち上げの増加理由について解説しています。
今回は人材派遣業の立ち上げ方と事業成功のための6つのポイントを解説しました。
ぜひ、人材ビジネス立ち上げの参考にしてください。
※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。
編集部では、人材紹介に関する様々な情報を無料で提供しています。お気軽にご登録ください!